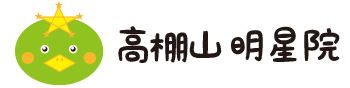- 天長5年(828年)河野家の祈願所
- 元禄2年(1689年)、松山城主久松定直(ひさまつさだなお)公の奥方の安産祈願
- 昭和25年(1950年)鐘楼の梵鐘を再鋳
観音様の由来

昭和53年(1978年)西国、坂東、秩父の百観音霊場の砂を清めて、百体の観音像を安置しました。
本堂の裏山の百観音像を順々に参拝しながら、山道を登って頂上にたどり着くと百観音堂があります。
この観音堂の中には、中央に救世観音像(ぐぜかんのんぞう)、左右に毘沙門天像(びしゃもんてんぞう)と不動明王像(ふどうみょうおうぞう)が並び、木の香りをただよわせ、力強く立っています。
この3体の仏像は、名松「与力松」が生まれ変わった姿なのです。
樹齢900年、高さ30メートル、根回り6・7メートルの巨木だった与力松は、小野地区のシンボルでもあり、伐採後地元の人たちが「名残惜しい。木はなくても、名松をしのぶよすがを。」と希望し、仏像を残すことになりました。
明星院15代住職髙山正全(たかやましょうぜん)氏の依頼で、小野出身の大西努(おおにしつとむ)氏が制作し、藤岡氏の協力もあって、昭和56年(1981年)に完成しました。
仏像の高さは、およそ62cmで、全体のバランスがよくとれています。顔には、生き生きとした表情が表れていて、威厳を感じる力作です。
本来、仏像にはヒノキ・クス・ケヤキなどがよく使われ、松は滅多にないそうですが、さすがは銘木。ヤニも少なく、しっとりとしていて、木目がそのまま仏様の衣装のように流れていて、よい材料だったそうです。
地元の人だけでなく、きっと姿を変えた与力松も喜んでいることでしょう。
そして、いつまでも、この山頂から、発展していく小野の町を見守ってくれるに違いありません。(ふるさと小野参照)